国際的な視点と現代アートに関する深い見識を持つ審査員により、国内外1,025組の応募の中から5組のファイナリストが選出されました。

金 光男きむ みつお

冨安 由真とみやす ゆま

原田 裕規はらだ ゆうき

村上 慧むらかみ さとし

やんツーやんつー
金 光男
きむ みつお
Artwork by Mitsuo Kim, Photo by Yusuke Suzuki (USKfoto)
ファイナリストコメント
この度、鷲田めるろ賞をいただき大変光栄に存じます。 ジャンク状態のアメリカ製のカヌーをレストアし、家族と水面を漕ぎ出した事が自身のアイデンティティと向き合うきっかけとなりました。2021年の個展の際に、実物のカヌーに蝋を満たした作品を発表すると同時に、蝋でできたカヌーの作品構想もしていました。この構想はなかなか実現するのが難しく、10年以内に発表できればと思っていましたが、今回TERRADA ART AWARDでファイナリストに選出されたことで制作し発表することができました。この作品を通して何が変わるかはまだ分かりかねますが、小さな小さな波紋が平和と希望に繋がる事を願います。最後に、タイトなスケジュールの中、この作品は決して一人の力では実現できませんでした。日常を支えてくれた家族と知恵や力を貸してくれた佐々木 麦帆氏、藤村 祥馬氏、山田 結子氏、森山 泰地氏、須賀 悠介氏、羽田野 皓紳氏、茂木 淳史氏、Artifact、鬣 恒太郎氏、鈴木 達也氏、志村 直人氏、LEESAYA 氏、乃村 拓郎氏に心から感謝の意を申し上げます。 金光男PROFILE
1987年大阪府生まれ。 2012年京都市立芸術大学大学院美術科絵画領域版画科修了。2016年『京都市芸術新人賞』受賞。主な展覧会に、個展『Blue Summer』(Der-Horng Art Gallery、2022年)、個展『グッド・バイ・マイ・ラブ』(LEESAYA、2021年)、『Positionalities』(@KCUA、2022年)、『PATinKyoto2016』(京都市美術館、2016年)、個展『APERTO 01 White light White heat』(金沢21世紀美術館、2014年)など。
「グッド・バイ・マイ・ラブ」(LEESAYA)展示風景 2021 Photo by Ichiro Mishima
冨安 由真
とみやす ゆま
Artwork by Yuma Tomiyasu, Photo by Yusuke Suzuki (USKfoto)
マジックミラーの構造は、こちらから見えていない時は向こう側からは見えているということである。今回展示する部屋の構造物の中にあるモニタリングカメラでは、構造物の外側にいる鑑賞者の様子も映っている筈だが、鑑賞者がモニターを見ることのできるタイミングでは、鑑賞者を映すことはない。この作品では、照明のプログラミングによって見える対象が強制的に移り変わることで、見ること・見えることという概念への揺さぶりを行う。
最終審査員コメント
「視点」という、美術において極めて原理的で、今までにも多くの作家が取り組んでいる命題に敢えて挑んだ冨安の本作は、今の時代を生きる本人ならではの作業と、その日常がコラージュされた、極めて奇妙で不安定な空間となっている。 その視点の「シフト」を作品の鑑賞行為に組み込み、空間が丁寧に描かれた平面作品や、空間を仕切る素材などを巧みに組み合わせながら、倉庫という無機質でサイトスペシフィックな作品の制作が難しい環境で展開した本作は、作品の鑑賞行為やその視点を揺さぶるだけでなく、そもそも作品とは一体何者であるか、改めて考えさせられる。 そしてこれから何に視点を合わせ、自身の作品として展開していくのか、冨安の眼差しが気になって仕方がない。 金島隆弘/金沢美術工芸大学 准教授ファイナリストコメント
この度は金島隆弘賞を頂きまして、大変光栄に思います。今回のプランは、かねてからやってみたいと温めていたアイディアを、寺田倉庫の無機質な倉庫空間に沿うような形でアップデートし落とし込んだものになります。実現にコストが掛かるプランですが、TERRADA ART AWARD の賞金として制作資金を提供していただけることから、実現が可能となりました。改めて感謝申し上げます。 プランが通り、実現できる喜びがある一方で、今回の作品は制作期間に戦争や震災などの世界情勢が重なったことで、私自身は制作をするということや芸術というもの自体への意味を自問自答する日々となり、制作に非常に苦しみました。今後もそういった問いはずっと続くと思いますが、それでも見ること・考えることを続けていきたいです。 最後に、審査員の皆さまや TERRADA ART AWARD スタッフの皆さま、そして制作チームの皆さまをはじめとして制作にご協力くださった皆さまに改めて御礼申し上げます。 冨安由真PROFILE
1983年広島県生まれ。ロンドン芸術大学チェルシー・カレッジ・オブ・アーツにて学部、修士修了後、2017年東京藝術大学にて博士号(美術)取得。見えないものや不確かな存在への知覚を鑑賞者に想起させる没入型のインスタレーション作品や絵画作品を発表する。主な展覧会に、個展『影にのぞむ』(原爆の図丸木美術館、2023年)、『瀬戸内国際芸術祭2022』(豊島、2022年)、個展『アペルト15 冨安由真 The Pale Horse』(金沢21世紀美術館、2021-22年)、個展『漂泊する幻影』(KAAT神奈川芸術劇場、2021年)など。主な受賞歴に、『第21回岡本太郎現代芸術賞』特別賞受賞(2018年)、『第12回shiseido art egg』入選(2018年)など。
「The Doom」(ART FRONT GALLERY)展示風景 2021 Photo by Masanobu Nishino
原田 裕規
はらだ ゆうき
Artwork by Yuki Harada, Photo by Katsura Muramatsu
かつて日本からハワイに渡った移民は、他文化・他言語との接触のなかで「ハワイ・ピジン英語」に代表されるトランスナショナルな文化を生み出してきました。彼/彼女らが経験したであろうプロセスを、言語学習のシャドーイング(復唱)による「声の重なり」と、作者である私の表情をデジタルヒューマンにトラッキング(同期)させる「感情の重なり」によって再演します。
遠くに行けば行くほど「私自身」に戻ってしまう人間の性(さが)と、それでもなお前進せざるを得ない人間の本性(ほんせい)。そのいびつで力強い歩みを空間全体で表現したい。
最終審査員コメント
ハワイの日系移民についてこの数年リサーチを進めてきた原田さんは、2023年夏に起きたマウイ島ラハイナの惨事に先立って地球温暖化や移民・難民という現代の緊急的な課題について真摯に目を向ける知覚をすでに備えていたと言える。他者の声に注意深く耳を傾け、土地の歴史・物語に触れ、それらを複合的に学び、新たな視覚言語で発信していく理解と表現のプロセスは、現世と彼岸をつなげる能の手法に触発されているようにもうかがえる。時空を超え、個の存在と社会、他者と私をつなげる複雑かつ複層的な要素を、デジタルテクノロジーを介してポートレート、語り、字幕を一画面の上に重ね合わせ編み込んでいく。こうして形を成す探求のキックオフに際し、これからの展開の可能性を期待したい。 神谷幸江/美術評論家、キュレーターファイナリストコメント
このたびは神谷幸江賞を受賞させていただき、大変光栄に思います。まずは本作で僕と一緒にシャドーイングをしてくれた日系アメリカ人の皆様(タイラー君、リーンさん、ラリーさん)に受賞の報告をしたいです。本作プランは数年前より温めていたものでしたが、実際に取り組んでみると、作品を実現するために 70名以上の方々の力が必要になることがわかりました。過去最大規模の制作の中で、苦しい局面も多々ありましたが、現代という時代性を反映した「新しい自画像」が立ち上がったように自負しています。それと同時に、自身が立ち上げたい表現の実現にはこれほど多くの人々が関わらざるを得ないんだということも改めて実感し、責任を感じました。次のステージに進む上で最大級の経験を積ませてくださった寺田倉庫の皆様、そして審査員の皆様に心から感謝しています。そして最後に、日系二世のラリーさんによる台本の「ピジン英語訳」を紹介させてください。やっぱり世の中で一ばんえらいのが人間のようでごいす/Go stay go Pakiki all da time ! Eh...no give up ‘til you pau !(直訳:いつだって抵抗する! ああ、最後まで諦めない!) 原田裕規
PROFILE
1989年山口県生まれ。とるにたらないにもかかわらず、社会のなかで広く認知されている視覚文化をモチーフに作品を制作している。2019年以降は断続的にハワイに滞在し、「ピジン英語」に代表されるトランスナショナルな文化的モチーフに着目。近年の個展に、『やっぱり世の中で一ばんえらいのが人間のようでごいす』(日本ハワイ移民資料館、2023年)、『Unreal Ecology』(京都芸術センター、2022年)、『Waiting for』(金沢21世紀美術館、2021年)。単著に、『とるにたらない美術』(ケンエレブックス、2023年)、『評伝クリスチャン・ラッセン』(中央公論新社、2023年)など。
《Shadowing》2023
村上 慧
むらかみ さとし
Artwork by Satoshi Murakami, Photo by Yusuke Suzuki (USKfoto)
舞台上で<茂み>が話しかけてくる、という夢を見た。なんの事情も知らされないまま舞台に上げられ、なにをすればいいのかもわからず困っている様子で、こちらまで哀しくなってしまった。そこにはある種普遍的な、産業革命の時代から現代までを貫く<不安>の形が現れているように感じられた。
同じころ、認知症気味の祖父が、廊下にあるコートハンガーを人だと思っていることが発覚した。私は、それは本当はコートハンガーでもなんでもない<なにか>で、歳を経て<認知将>となった人間だけが、その存在に気づくことができる、という可能性について考えた。
そして、これらの体験に作品という形を与えるとき、ドローイングにおける「輪郭線」の問題も同時に考えられるのではないか、というひらめきがあった。ひいては「フィクションとノンフィクション」、あるいは「記憶と捏造」の二項対立図式も超えていけるのではないかと、そう思えた。
最終審査員コメント
村上の作品では現実世界の些細な出来事から始まり、それがどのようにして創造的なハルシネーションを経て物語へと変貌し、さらにその物語が演劇表現を経て仮想空間での創造的な展開へと進化していくのか、というプロセスに強く惹かれました。日常の風景に独特な方法で変化を加えることによって見慣れた世界に対する新しい視点と発見を提供し、日常の美や問題を再発見させてくれます。この貴重な機会を最大限に利用していただきたいと思います。引き続き自由な発想と創造的な精神で挑戦的な作品を生み出してください。楽しみにしています。 真鍋大度/ライゾマティクス ファウンダー、アーティスト、インタラクションデザイナー、プログラマ、DJファイナリストコメント
これまで試したことのない、自分にも新しい作品を実作する素晴らしい機会を提供してくれたTERRADA ART AWARDと、賞に選んでくださった真鍋大度さん、そしてなにより演出ですばらしい仕事をしてくださった村社祐太朗さん、長期間の制作に並走してくれた本間大悟さんと増田義基さん、そのほか、文字数の関係で一人一人のお名前を挙げることができないのが心苦しいのですが、本作品の制作を助けてくれた総勢23名の皆さんにこの場を借りてお礼申し上げます。ほんとうにありがとうございました。制作にあたり、現実とはなにかということを考えてきましたが、そんなすべてが馬鹿馬鹿しくなってしまうような「現実」の理不尽さのなかで、この光栄なる受賞を心から喜ぶことを阻害してくるような、パレスチナの情勢や能登半島地震にまつわる為政者の不手際など、社会状況が腹立たしい限りですが、今後もこの賞に恥じないよう自分にできることを淡々と続けていきます。 村上慧PROFILE
1988年東京都生まれ。2011年武蔵野美術大学造形学部建築学科卒業。自作した発泡スチロール製の家に住む《移住を生活する》、広告収入を使って看板の中で生活する《広告看板の家》などのプロジェクトを行っている。主な個展に、『村上慧 移住を生活する』(金沢21世紀美術館、2020年)、主なグループ展に、『高松コンテンポラリーアート・アニュアル vol.08』(高松市美術館、2019年)などがある。主な著書に、『家をせおって歩いた』(夕書房)など。
《移住を生活する 東京2020 / Living migration Tokyo 2020》 2020 Photo by Ryo Uchida
やんツー
やんつー
Artwork by yang02, Photo by Yusuke Suzuki (USKfoto)
※本作は装置による演劇作品です。
※上映時間(各30分)平日17:00~、土日15:00~/17:00~
最終審査員コメント
やんツーの作品には、手作業の痕跡はない。テクノロジーを駆使し、無人で機械的に事前プログラミングされた作品は一見無機質で、その先に冷静沈着な理系作家を想像させる。しかし個別の作品の根底に流れる信念は、誤解を恐れずにいえば、誰よりもナイーブで泥臭く、極めて人間らしい。資本主義に呑み込まれるアート。消費されていくアート。愛でられずひたすら倉庫に保管されるアート。美術そのものがもつ空虚さをシニカルなユーモアで斬っていく。美術をやる意義、意味、意図。 でも、そんなテーマの作品を制作する彼が、こうやって高額賞金の出る倉庫会社主催のど真ん中アートアウォードにチャレンジしてみたりする。この矛盾との絶妙な混在こそが、やんツーという作家の醍醐味だと思う。みんな、理想とリアルの境界線で必死に闘っている。彼もそう。私もそうだ。この素晴らしき才能に、審査員の中で最もアートマーケットに近い立場で美術に関わっている寺瀬由紀賞をお渡しすることで、もっともっと迷わせて、更に良い作品を制作してもらいたい。期待しています。 寺瀬由紀/アートインテリジェンスグローバル ファウンディング・パートナーファイナリストコメント
最終審査のプラン提出〆切日が6月末日で、自分の個展のオープニングを4日後に控え、何もかも間に合っておらず絶望の中、設営中のギャラリーの中で暑さにうなだれながら半ば苦し紛れにせめて形だけでもと、たった2枚のPDFにプランをまとめ提出したのを覚えています。満足のいく資料を出せず、当然落選するだろうと思っていたので、ファイナリスト選出通知を受けた時は本当に信じられないという思いでした。結果的に、このような素晴らしい展覧会の機会に恵まれ、関係者の方々には連日朝から晩まで続く設営にお付き合いいただき、とても感謝しています、ありがとうございました。そして、賜りました寺瀬由紀賞ですが、今回、美術の制度の中でも、特に美術館や倉庫、アートマーケットの文脈にアプローチした作品プランだったので、マーケットのど真ん中にいる寺瀬さんが評価してくれたら面白いなという目論見が元々ありました。なので、この審査員賞も本当に嬉しく、今後の作家活動の糧になっていくと思います。 やんツーPROFILE
1984年神奈川県生まれ。2009年多摩美術大学大学院修了。菅野創との共同作品が『文化庁メディア芸術祭』アート部門にて新人賞(第15回)、優秀賞(第21回)を受賞。近年の主な展覧会に、『六本木クロッシング2022展:往来オーライ!』(森美術館、2022年)、『遠い誰か、ことのありか』(札幌文化芸術交流センター、2021年)、『DOMANI・明日展』(国立新美術館、2018年)、『あいちトリエンナーレ2016』(愛知県美術館、2016年)など。
《永続的な一過性》2022 Photo by Naoki Takehisa
ファイナリスト展
「TERRADA ART AWARD 2023 ファイナリスト展」では、倉庫をリノベーションした当社イベントスペース「寺田倉庫 G3-6F」を舞台に、ファイナリスト5 組が「TERRADA ART AWARD 2023」へエントリーした展示プランによって独自の展示を創り上げ、未発表の新作を含む作品を個展形式で発表します。
- 会期
- 2024年1月10日(水)~1月28日(日)
※ 会期中無休
※ 2024年1月10日(水)は招待者のみ入場可能 - 時間
- 11:00〜18:00(最終入館17:30)
- 入場料
- 無料
- 会場
- 寺田倉庫 G3-6F(東京都品川区東品川2-6-10 寺田倉庫G号)Google Map
- アクセス
- 東京モノレール羽田空港線
天王洲アイル駅中央口 徒歩5分
東京臨海高速鉄道りんかい線
天王洲アイル駅B出口 徒歩4分※ 施設内に駐車場はございません。お近くの有料駐車場をご利用ください。
- 助成
- 公益財団法人東京都歴史文化財団 アーツカウンシル東京【芸術文化魅力創出助成】
ファイナリスト紹介
「TERRADA ART AWARD 2023」のファイナリスト5組を、インタビューや「TERRADA ART AWARD 2023 ファイナリスト展」の展示風景を交じえご紹介いたします。
TERRADA ART AWARD 2023 ファイナリスト紹介ムービー(約4分) Filmed & Edited by SUZUKI Yusuke (USKfoto)
最終審査員 × ファイナリスト オンライン対談
最終審査員とそれぞれ各審査員賞を受賞したファイナリストとのオンライン対談を実施しました。
金島隆弘 x 冨安由真
神谷幸江 x 原田裕規
寺瀬由紀 x やんツー
真鍋大度 x 村上慧
鷲田めるろ x 金光男
審査員総評
最終審査員 (二次審査を終えて)
金島 隆弘
金沢美術工芸大学 准教授
秀作の揃った前回より続けて最終審査を担当させていただき、今回も実際の展示として作品を観てみたいと思う提案が多くあった中で臨んだ審査会でしたが、コンセプトの説明に重きが置かれ、具体的な作品の内容や展示プランをイメージしにくい発表や、目先の情報に作品が引っ張られ、自身と社会との接続性が希薄な作品の提案が多い印象でした。アウォードを機に自分が制作したい、挑戦したい、実験したい、という作家としての強い意思が伝わってくる発表が思いの外少ない中、惜しくも受賞まであと一歩という作家もいましたが、ファイナリストに選ばれた5名は、今までの活動や制作を踏まえながら自分が新たに取り組んでみたいこと、そして社会の中で自分という存在が何者なのかを作品を通じて考え続けることを素直に伝えようとする姿勢を感じました。これから実際の展示に向け、その強い思いが具体的な作品として立ち上がり、展開していくことを期待したいと思います。
神谷 幸江
美術評論家、キュレーター
制作に駆り立てるモチベーションが、自分を見つめることに始まっていい。非常に多くのプロポーザルが「私」を語ることに始まり、自身の出自や体験に真摯に向き合っていた。けれどもその考求の多くが各々の個人空間に留まったままでいる。個人的なことは政治的なこと(The personal is political.)なのだ。ダイナミックな変化にうねる世界に向け、どう繋がり鍵手をかけるのか。社会政治的な構造に疑いを持ち、個と世界との関わりを分析・探求することは、作品の深度と強度を高めるのに必要なプラクティスでもある。TERRADA ART AWARD 2023に臨んだ応募者の中でファイナリストたちは、美術という表現を通じ、グローバルな世界への問いかけと発信の一石を投じる試みに、果敢な一歩を踏み出していた。寺瀬 由紀
アートインテリジェンスグローバル ファウンディング・パートナー
再スタートして2回目となるTERRADA ART AWARD、今回も数多くの応募があったようで、早くも国内で有数の公募展とアーティストの皆さんに認識されていることを喜ばしく思います。最終審査にあたっては、過去の作品制作ポートフォリオにおけるコンセプトやアウトプットは非常に興味深いのに、そこから最終展示案に舞台を移す際への表現展開が乏しいケースも多々見られました。また、パーソナルな関心やテーマを通じてユニバーサルに訴えかける作品への展開を目指すべきところ、極めて個人的な世界観の中で物語が終始完結してしまい、受け手のオーディエンスが作品からの最終メッセージを読み解き難いというケースも多かったように思います。
そんな中で今回最後まで残った5名のアーティストの皆さんは、与えられた表現舞台における言語化の手法と、なぜ今ここで自分がその作品を作りたいのかの理由づけが明確に確立されていたと思います。グローバルな舞台で活躍できるアーティストを支援するという本アウォードの設立趣旨に鑑みると、これらの能力を兼ね備えることはまさに必要不可欠であり、今回は残念ながら選考に残らなかったアーティストの皆さんも、今後もこのような公募展へのチャレンジを重ねて、少しでも表現者としての経験値を積んでいっていただければと思います。
真鍋 大度
ライゾマティクス ファウンダー、アーティスト、インタラクションデザイナー、プログラマ、DJ
エントリーされた多数の作品を拝見し、その制作の背景や研究テーマが、しばしば作家の個人的な体験に端を発しているのは非常に興味深く、その後の展開が社会や政治的なテーマへと洗練されていることに感銘を受けました。しかしながら、そのテーマの深さや複雑さを、視覚的・空間的な表現へと完全に昇華させている作品は少数に留まるように見受けられました。グローバルな視点を取り入れることに挑戦している作家が多い中、一部の作品では普遍的とされる視点の繰り返しや、社会事象に対する感受性の欠如が目立ちました。それでも、中には作者の熱意や探求心が鮮明に伝わる作品もあり、審査員たちの共感を引き出し、今回の評価で特に印象的であったのではないかと感じております。鷲田 めるろ
十和田市現代美術館 館長、東京藝術大学 准教授
金は、パラフィンワックスという、つるつるとした、上にインクが定着しにくい素材をあえて用いることによって、シルクスクリーンによる重層的な平面作品を生み出してきた。今回は、パラフィンワックスでできたカヌーの形の立体と平面を組み合わせる。会期中、ゆっくりとそのワックスが溶けていく様子を見せることによって、ワックスの素材感が観客により伝わりやすくなると予想される。日常の中にある不安感の表現を得意とする冨安は今回、「リミナル・スペース」に着目する。冨安の特徴である手触りのある中古家具を用いることを封印し、無機質なオフィス家具を使うことが新たな挑戦となるだろう。
原田は、「フェイストラッキング」というデジタル技術を用いて移民のテーマに取り組む。デジタルの「コピー」と、美術における「写し」という、それぞれ大きなテーマが架橋されることを期待したい。
村上は、「家を背負って移動し、住み込む」という代表作ではなく、さまざまなオブジェを演劇的に繋げてゆくというプラン。平面状の輪郭と、立体とを繋ぐ表現に新たな展開への期待が膨らむ。
やんツーは展示実績のある要素を組み合わせた計画で、実現可能性の点で最も信頼できる提案。アウォードの主体と会場である「倉庫」という文脈にも適合する。
審査の過程では、ジェンダー、移民といったテーマの作品も多くあったが、最終的に金と原田の作品しか残すことができなかったのは心残りである。それらの作品は映像を表現手段とするものも多く、作品の中心となる映像の内容が審査の段階で詰めきれていなかったことも、残しづらかった要因の一つであった。他方、村上、やんツーの演劇的な表現は、本アウォードに新たな展開をもたらすだろう。
一次審査員
池城 良
アーティスト、ミュージシャン、研究者、香港城市大学クリエイティブメディア学部 助教授
ポートフォリオには、それぞれの作家の芸術活動の有無や人生経験の豊富さが反映されていましたが、その差は年齢層が高いほど一層顕著でした。また、社会・政治問題を直視する作品の他に、幻想的な世界や現実と空想の間の領域を描き出す作品が増えているようにも思えました。これら様々な表現手法の中で、自分自身をどう映し出すか、または映し出さないか、それもまた個々に異なり、多様性の重要さを改めて感じました。ファイナリストや一次審査通過者、そしてTERRADA ART AWARDに応募された皆様が今後も自分が納得できる芸術活動と人生を歩み続けられることを心から願っています。
大巻 伸嗣
美術作家
はじめて一次審査に参加し、1,000通近い応募者それぞれに目を通す中で、アーティストとしての活動に対して高い意識を持っている作家が多く見受けられたのは大変好感がもてた。また、コンテンポラリーダンスなどの身体表現の応募があったことも新鮮であった。幅広いジャンルで応募があったのがとても興味深く、最終的に選ぶのにかなり迷いながら何度も企画書や映像を見返した。この時代の不確かさや、実態に対する実感を探るような作品が多く見られたのも大変興味深かった。コンセプトや言葉はとても大切だが、それ以上に実際の作品から感じ取れるような力がある作品もあったように思う。このような公募では、残っていくのは難しいかもしれないが、作品を作り続けていくことが今後のチャンスにつながると考えるので作家活動を続けていってほしいと思う。ファイナリストの皆さんの作品を実際に見ることができるのが楽しみだ。
木村 絵理子
キュレーター、弘前れんが倉庫美術館副館長兼学芸統括
今回はじめて本アウォードの審査に参加して、形を変えて2回目となるこのアウォードの方向性を定めていく役割を担う責任を感じながら選考にあたりました。審査会で協議を重ねながら進める審査とは異なり、一人で行う審査の過程では、審査員各々の考えがより強く反映されることになります。応募者の年齢や経験、表現領域の幅広さに特色のある本アウォードにおいて、今日的なトピックに取り組むアーティストたちをできるだけ偏りなく選考することに務めました。応募された作品は、昨今の潮流を反映するように、歴史との関係性を掘り下げた作品や、ニューメディアとの関係の中で獲得した新たな身体性について言及するような作品が多く見られました。一方で、人間社会の範疇を超えた他者との関係に言及するようなスケール感を感じさせる作品は少なく、地球規模の課題に向き合おうとする世界的なアートの潮流と、日本のそれとの差異について、考えるきっかけともなりました。高橋 龍太郎
精神科医、現代アートコレクター
「悪い場所」と言われて何年たったでしょうか。「悪い場所」という批評性のないまま、同じことを繰り返す歴史は一体誰に責任があるのでしょうか。作家の問題なのか?それをサポートする側の力が足りないのか?あるいは健全な批判精神が育っていないことが、根本的な問題なのか?
それらが総合的に絡み合って身構えできなくなっている気もします。
ではどうするか。今回の作家たちは、多くは知った人たちで大きな発見はありませんでしたが、サポートする側がTERRADA ART AWARDのように力を発揮してくれれば、局面は変わっていくのでしょうか?今はそれを期待するしかないですが、みんな少しお行儀が良過ぎるように感じました。昔はアートシーンでは貧しかったけれど、もっとエネルギーに溢れ、もっと論争をしたように思います。
論評のまとめは、「もっと論争しろよ」です。
竹久 侑
キュレーター、水戸芸術館現代美術センター 芸術監督
18歳から45歳まで、それぞれ多様な表現領域で活動する、さまざまなキャリアの方たちから応募がありました。その多様性と応募数が、TERRADA ART AWARDが用意した、若手から中堅のアーティストに対し、きちんと相応の予算(賞金)をつけて制作と発表の機会を提供するプラットフォームそのもののニーズを示していると思いました。翻せば、とくに若手アーティストが表現の手法や形態を問わず、ギャラリーで作品を発表する機会を予算つきで得られる公募システム自体が、とても少ないことを表しているのだろうと思います。ニーズを捉えた公募アウォードだからこそ、TERRADA ART AWARDは前回に続き、たいへん多くの応募を集め、一つ一つを審査する一次審査は審査員とのガチンコ勝負でした。
審査を終えて思うことは、やはり芸術とは何かを自分なりに突き詰める姿勢が問われるということ。そして、キャリアのある方たちには、これまでの実践をいかに発展・展開させていくかにこそ期待を寄せているということです。
椿 玲子
森美術館キュレーター
デジタル系、インタラクティブ系、ゲーム系、ヴァーチャルとリアルを繋ぐような表現が増えてきていると感じました。ただ、応募作品を全体的に見ると表現手法は様々です。また歴史の再認識、ジェンダーやマイノリティの解放、自然と人間の関係、デジタルによる社会の変容などがテーマとなったものなどが気になりました。何をアートとするのかは、常に問われてきたことなのですが、今もまた問われているのだなと改めて感じました。
本当に多くの応募が、色々な地域からあり、また色々な表現があることに可能性を感じました。もちろん、審査は大変でした!ただ、あの資料で自分を分かってもらうにはどうしたら良いか、頑張っている人とそうでない人の差も大きかったです。あと。映像のリンクはあるのに実際には機能していない応募も結構多数あり、それはとても残念でした!
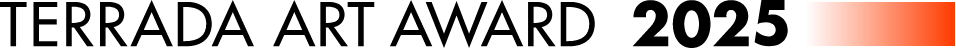























最終審査員コメント
カヌーは以前から金がモチーフとしてきたものである。カヌーは、韓国と日本の間という金のアイデンティティと関わり、「間」を象徴するものであろう。これまでは実物のカヌーの中を蝋で満たすような作品であったのに対し、今回はカヌー自体を蝋でつくり、全体が溶けて輪郭も変化する計画である。そのことによって、カヌーの脆弱性がより明確になり、作品の強度が増すはずだ。この点が、今回の新作に期待を寄せた理由の一つである。さらに、蝋という素材は、単に溶ける素材として選ばれているだけでなく、一緒に展示される平面作品の素材でもある。そのことが立体と平面を統合し、展示物同士の関連性を高めている。この点が、金の展示構成を高く評価したもう一つの理由である。 鷲田めるろ/十和田市現代美術館 館長、東京藝術大学 准教授